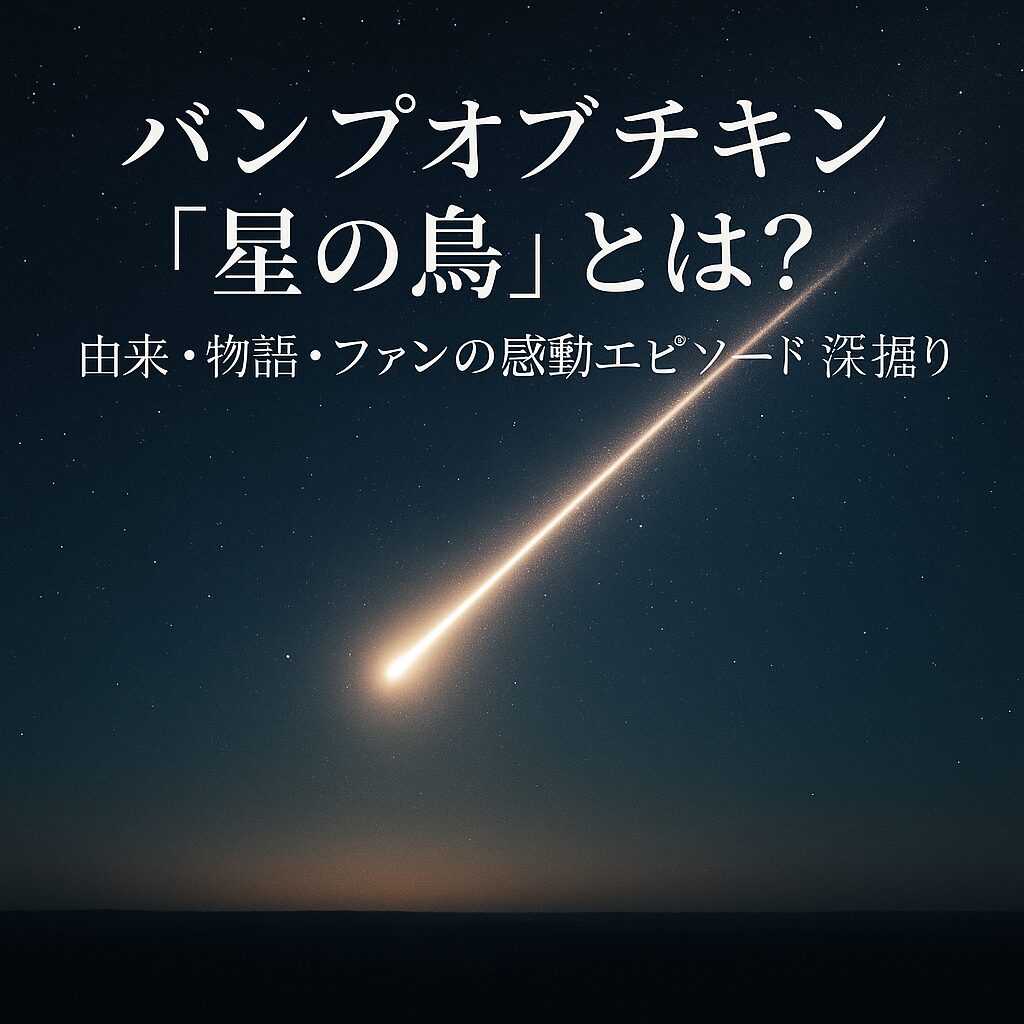バンプオブチキン『星の鳥』とは、一体どんな意味を持つ楽曲なのでしょうか?その美しいタイトルの由来や、歌詞に込められた想いを知ると、さらに深くこの曲に惹きこまれてしまいます。
2007年にリリースされたアルバム『orbital period』に収録された『星の鳥』は、ただの“前奏曲”では語れないほどの深みとストーリーを内包しています。メンバーが語ったインタビューや制作秘話を辿ることで、バンプらしさが詰まった一曲の本質が見えてきます。
この記事では、『星の鳥』の意味や由来、そしてファンの間でも語り継がれる魅力をたっぷりとご紹介します。
バンプオブチキン『星の鳥』とは?その意味と世界観に迫る

『星の鳥』とは、アルバム『orbital period』の冒頭に配置されたインストゥルメンタルの楽曲です。続く『メーデー』と共に、まるで“物語のプロローグ”のような役割を果たしており、楽曲全体にテーマ性を持たせる象徴的な存在です。
バンプオブチキンのボーカル・藤原基央さんは、インタビューでこう語っています。
「“星の鳥”は“希望の象徴”のような存在として生まれました。アルバム全体を通して、宇宙や命の循環を感じられるような構成にしたかった。」
この発言からもわかるように、『星の鳥』は単なる楽曲以上の意味を持ち、作品全体の“軌道(orbital)”を形作る重要なピースとなっています。
ファンの間でも、“星の鳥が空を飛び、物語が始まる”というイメージが共有されており、まさにバンプオブチキンならではの叙情的世界観が感じられます。
ちなみにこの曲はライブではあまり演奏されることはありませんが、それがまた“特別な楽曲”としての印象を強くしています。
『星の鳥』の由来とは?タイトルに込められたメッセージ
『星の鳥』という不思議で美しいタイトルには、どのような意味が込められているのでしょうか?この問いに対し、藤原さんは過去のインタビューで、タイトルの発想についてこう語っています。
「“星”と“鳥”って、本来は全く違う存在なのに、どちらも“遠くを見つめる象徴”なんですよね。星は夜空の彼方にあって、鳥は空を自由に飛ぶ。その2つを重ねることで、希望とか、旅立ちとか、そんなテーマを重ねたかったんです。」
この言葉からも分かるように、『星の鳥』というタイトルは、単なるファンタジックな響きではなく、リスナーに“物語の始まり”を意識させる役割を持っています。見上げた空の先にある“希望の光”としての星。そこへ飛び立とうとする“意志”を持った鳥。2つが重なったとき、バンプオブチキンらしい壮大で繊細な世界が立ち上がるのです。
また、アルバム『orbital period』の曲順をよく見ると、『星の鳥』『メーデー』『才悩人応援歌』『プラネタリウム』といった、天体や救済を思わせるモチーフが随所に散りばめられており、『星の鳥』が「旅のはじまり」を象徴する存在であることが明確になります。
由来をたどると、藤原さんが幼少期から空や星が好きだったというエピソードにも繋がります。自身の孤独や感情を空に投影していたという話は、彼の楽曲の多くに流れる“宇宙的な孤独と希望”というテーマの根底にあります。
つまり『星の鳥』とは、“自分の居場所を探して旅立つ心”そのものであり、聴く者に「ここではないどこかへ飛び立つ勇気」を与えてくれるのです。
バンプオブチキンが描く“星の鳥”の物語と歌詞の解釈
『星の鳥』はインストゥルメンタル(歌詞なし)の楽曲ですが、そこに込められた“物語”や“歌詞のような意味”を感じ取るファンは少なくありません。
藤原基央さんは『orbital period』というアルバムを「一冊の小説のように聴いてほしい」と語っており、『星の鳥』はその“第1章”にあたる存在。つまり、物語を始める「語り手の目線」や「世界の始まり」のような役割を果たしているのです。
この楽曲のあとに配置されている『メーデー』では、人間の孤独や葛藤、救済への渇望が描かれます。その前に『星の鳥』を配置することで、「希望が生まれ、しかしすぐに困難にぶつかる」というドラマの導入部が自然に成立するのです。
実際、ファンの間では『星の鳥』を“言葉にならない想い”や“祈り”と解釈する声も多く、「あの旋律だけで涙が出る」「言葉がないからこそ想像が膨らむ」といった感想がSNSでも頻繁に見られます。
また、音楽評論家の間でも『星の鳥』の旋律構成は高く評価されており、主旋律の展開やアレンジから「旅立ち」「覚醒」「孤高の魂」などを読み取る評論が紹介されることもあります。
「言葉ではなく音で語る。この曲があることで、アルバム全体の説得力が一気に増した」― 音楽ライター・O氏のコメント
“歌詞がない曲なのに、心の奥に歌が流れる”――まさにそれが『星の鳥』という楽曲の魔法であり、バンプオブチキンの音楽性の真骨頂なのです。
『星の鳥』とは何かを知る上で外せないアルバム『orbital period』
『星の鳥』という楽曲を理解するには、その収録アルバムである『orbital period』の全体像を知ることが欠かせません。このアルバムは、2007年12月19日にリリースされ、バンプオブチキンにとって4年ぶりとなるフルアルバムでした。
タイトルの「orbital period(軌道周期)」には、“星が巡る道”という意味が込められており、まさに宇宙や生命の循環をテーマにした作品です。収録曲には『メーデー』『花の名』『カルマ』『supernova』『arrows』など、バンプの代表曲が多数含まれており、それぞれが“星の物語”の一章を担っています。
その冒頭に配置された『星の鳥』は、まさに“旅立ち”の合図。アルバムを手に取ったリスナーの心に、物語の扉を開くような静かな衝撃を与える楽曲です。続く『メーデー』では突きつけられる現実の重みが描かれるため、『星の鳥』が持つ透明感は、対比としても非常に効果的に作用しています。
「このアルバムは、一つひとつの曲が星のように散らばっていて、それをつなぐ軌道が『星の鳥』なんです」
――藤原基央(当時のインタビューより)
また、このアルバムの初回限定盤には『星の鳥/メーデー絵本』が同梱されており、楽曲の世界観がビジュアルとしても展開されました。物語と音楽が一体となったこの試みは、当時のファンの間でも大きな話題となり、「バンプが提示する新しい音楽の形」として高く評価されました。
こうして『星の鳥』は、アルバム全体の世界を象徴し、導いていく“道標”のような存在となっているのです。
ファンが語る『星の鳥』の魅力とは?感動エピソード紹介
『星の鳥』はインストゥルメンタルという形にもかかわらず、リスナーの心に深く刻まれる楽曲として、多くのファンに愛されています。実際にSNSやブログでは、以下のような声が見られます。
「初めて『orbital period』を聴いたとき、最初の音だけで涙が出ました。言葉がないのに感情があふれる。それがバンプのすごさだと思う。」
「就職で上京する前夜、緊張と不安で眠れなかった時に聴いたのが『星の鳥』でした。まるで“飛び立て”って背中を押されている気がして、泣きながら眠りました。」
また、ライブでこの曲が流れた瞬間に涙するファンも少なくありません。照明が落ち、静かに鳴り始めるあの旋律には、まるで時間が止まったかのような神聖さがあります。
ファンの間では“この曲を聴くと、自分の人生の軌道(オービタル)を振り返ってしまう”という声もあり、『星の鳥』は一人ひとりの人生と密かにリンクしている存在だとも言えるでしょう。
あるファンは、自身の結婚式の入場曲に『星の鳥』を選んだと語ってくれました。言葉で語るよりも、この旋律が自分たちの“旅立ち”を象徴してくれたといいます。そんな風に、一人ひとりの人生の大切な場面に寄り添うことができる音楽、それが『星の鳥』の本当の魅力なのです。
【まとめ】バンプオブチキン『星の鳥』とは?その由来と意味をもう一度
バンプオブチキン『星の鳥』とは、一言で言えば「言葉を持たない物語の始まり」です。インストゥルメンタルでありながら、心に響く旋律は、聴く人それぞれの“旅立ち”や“希望”と重なり、深い感動を与えてくれます。
そのタイトルの由来には、藤原基央さんの「星と鳥、どちらも遠くを見つめる象徴として重ね合わせた」という詩的な意図が込められており、アルバム『orbital period』全体の世界観を象徴する重要な楽曲でもあります。
歌詞のない曲だからこそ、リスナーが自由に自分の物語を重ねることができる。だからこそ、『星の鳥』は多くの人にとって“心の支え”となり、“人生の節目”にそっと寄り添う存在なのです。
あなたにとっての『星の鳥』は、どんな物語を運んできてくれましたか? もしまだ聴いたことがないという方は、ぜひアルバム『orbital period』を通して、その旋律の意味を感じてみてください。
▼ バンプオブチキンの最新情報や楽曲詳細は、
BUMP OF CHICKEN公式サイトをご覧ください。